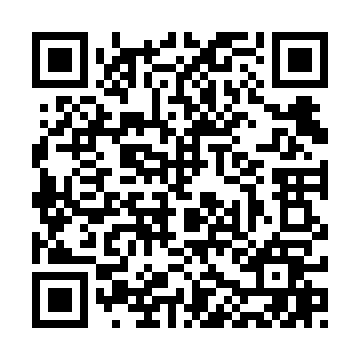検索結果の簡素化と一部構造化データのサポート終了について思うこと
Publish2025/11/12(水)

今回は久々に検索結果関連のことを書こうと思います。
今回取り上げるテーマはGoogleが行っている検索結果画面を簡素化していこうという方向で動いていることについて。
以下の記事で紹介されているように、「2026年1月以降、Search ConsoleとそのAPIでは構造化データタイプのサポートを終了します。」と明記されています。
https://developers.google.com/search/blog/2025/11/update-on-our-efforts
以前のGoogle Search Central Blogでも検索結果を簡素化するために一部の構造化データを廃止すると明記してありました。
廃止されるリストに挙げられていたのは「書籍アクション、コース情報、主張の審査、給与推定額、学習用動画、特別なお知らせ、車両リスティング」など、使用用途がかなり限定的なものだけだったので特に気にしなくていいかなと思ってスルーしてましたが、今回の記事で更に追加で情報を出してきたことで、この方向性は現在Googleが向かっている方向なんだろうなと改めて思っています。
検索結果を簡素化したいとは何かを考える
ここからは僕が考えることについて書こうと思うのですが、なぜGoogleは検索結果画面を簡素化したいのでしょうか。
構造化データが採用された背景としては、検索結果画面をリッチコンテンツ化する(検索結果画面のリッチスニペットの範囲拡大という方向性)事にあったと思っているのですが、現在はそれが求められていないという結果が出たんでしょうね。
例えば、廃止が検討されている構造化データのクリック率が悪いというデータが出たとか、その構造化データが表示される検索結果でのエンゲージメント率が悪いとか、そういう事がわかってきたのでそれならやめようということになった可能性があると思うんです。
また、現在の検索結果はAIによる要約なども含めてかなりごちゃごちゃしてきた感じがあるので、構造化データの効果が減少している、表示させるための負荷の高さに見合った効果が期待できないなどのパフォーマンス面での問題点があるのかもしれません。
いずれにしても、Googleが検索結果画面の簡素化をしているという方向性は把握しておく必要があり、webサイトやホームページを運用している我々は、その前提のもとに検索結果での表示の変化を確認しておく必要がありますね。
こういう系統の時代の変化には今後も注視しておこうと思います。