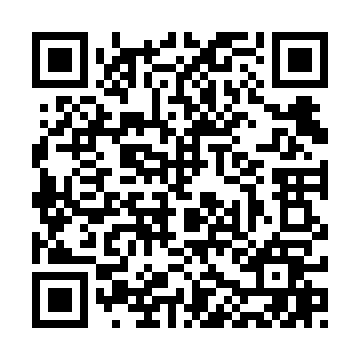GEO/LLMO(生成AIエンジン最適化)でのweb集客の考え方
Publish2025/05/13(火)

今回は、GEO/LLMOでの集客について色々考えてみたので、まとめてみようと思います。
GEOはGenerative Engine Optimizationの略で、LLMOはLarge Language Model Optimizationの略で、簡単にいうと生成AIからの流入増加を最適化させようという手法です。
わかりやすくいうと、SEOが検索エンジンからの流入増加施策として一般的ですが、GEO/LLMOが生成AIからの流入増加施策という位置付けになります。
なお、GEO/LLMOはまだ一般的な名称として浸透しているわけではない(GEOと検索するとビデオレンタルのゲオばかりが出てくる現状を考えると)ので、今後この施策の名称が変更になる可能性はあります。
また、現時点でこれから記載する内容が最適ではなくなる可能性も普通にあるので、あくまで考え方として参考にしてもらった上で、実際に試してみて実感を得ることをお勧めします。
GEO/LLMOを行う意味
GEO/LLMOは、生成AIを活用してユーザーに最適化された体験を提供し、集客につなげる新しいアプローチとなります。
生成AIが登場する以前の時代では、web集客はSEO/web広告/Referral(被リンクetc)/SNS/メルマガなどが主流になっていましたが、この中に生成AIからの参照が追加されるというイメージになります。
web集客の新しい選択肢が増えているので、ここに注目をするのはある種の必然になります。
実際に、ふにすでサポートをしている企業のホームページでもGEO/LLMOでの集客とみられる数値が増加してきており、場合によっては全体の1割程度を占めているケースもあります。
今後、生成AIがさらに活発に利用されていく時代になることは明らかなので、その比率も上がってくることが考えられます。
そう考えると、今の時点から生成AI経由のアクセスに注目し、対応を行なっていくことで今後の展開も変わってくるはずです。
GEO/LLMOの特徴とポイント
GEO/LLMOの特徴として考えられるのは、ユーザーごとに異なる体験を提供できるかどうかです。
具体的には、生成AIはユーザーの検索意図や履歴などを基に、パーソナライズされたコンテンツやおすすめ情報、対話などをリアルタイムに生成して提供する仕組みです。
その提供された情報でユーザーの理解力と購買意欲を促進するなどして、最終的に購買や問い合わせといったアクションを促します。
ひとりひとりに合わせた体験を提供することで、より深い顧客関係を構築するという特徴があります。
そのため、生成AIから提示される内容に対しての信頼性が高い状態になるので、そこで自社のコンテンツが紹介されれば、これまでよりも目的意識の高いお客さんに自社商品やサービスを推薦してもらえるようになります。
そのために、自社商品やサービスがどういうシーンでどこの誰にどのように使用されるのかを想定し、そのパターンごとにユースケースや実績を提供できているかどうかがポイントになります。
SEO/LLMOとGEOのどちらを優先させるのかについて
GEO/LLMOのことを考えると、他の施策への影響ということも考えなければいけないポイントです。
特にコンテンツの内容が結果に大きく影響するということを考えるとSEOとの関係は非常に注目すべきポイントです。
ここからは個人的な見解となりますが、基本的にはGEO/LLMOはSEOの延長線上にあるものだと思っているので、これまで通りのSEO(SEO自体の考え方によっては必ずしもそうとは言えない場合もあるので判断が難しいこともあるのですが)をしていれば、結果的にGEO/LLMOにもいい影響を与えると思っています。
というのにも理由があって、ふにすでサポートをしている企業のホームページでの実例でも生成AIからのアクセスが増加しており、GEO/LLMOとして特別に施策を行なっていることがない状態でもアクセスが増加しているためです。
この増加したアクセス分は、行なっているSEO視点での施策の影響を受けているので、SEOをきちんと適切に実施していればGEO/LLMOでも結果につながるということを実感しているためです。
GEO/LLMOは、SEOの基本的な考え方を土台としつつ、生成AIの特徴を理解することで結果につながってきます。
SEOで重要なキーワード最適化やコンテンツの質の考え方が、生成AIがユーザーに価値ある情報を提供するための基盤となります。
生成AIは、SEOで特定されたキーワードに基づいて、多様な形式のコンテンツを効率的に生成し、ユーザーの様々なニーズに応えることができるので、SEOでホームページの質を高めることが、生成AIが提供するに体験の質の向上に役立ち、相乗的な集客効果が期待できるようになります。
SEOとGEO/LLMOを別の施策として考えるのではなく、統合的な戦略として考えることが重要です。
GEO/LLMOを意識したコンテンツ作成時のポイント
GEO/LLMOを意識したコンテンツ作成のポイントとしては、「パーソナライズ」「インタラクティブ」「タイムリー」の3つの要素を考えましょう。
生成AIがユーザーの興味や関心に合わせてコンテンツを自動生成するとはいえ、その基となるデータや指示出しが重要です。
ユーザーの検索意図を深く理解し、検索意図に応じた最適なコンテンツ(テキスト、画像、動画、対話形式など)を準備しておくことで、生成AIが作成するコンテンツに自社の内容を盛り込んでもらえるようになってきます。
単に情報を羅列するのではなく、ユーザーの不安や不満を解消し、リアルタイムで満足感を得られるコンテンツ作成を意識することが大切かと思います。
また、生成AIがコンテンツを利用する場合は、なるべく簡潔に見出しと内容を整理すると効果的だと言われています。
実際に根拠があるわけではないのですが、ユーザーが利用できる時間の少ない中で内容を簡潔にわかりやすく提供することはSEO視点でも重要な要素なので、コンテンツ作成時には「簡潔に、わかりやすく」ということを意識することも効果が出るポイントであると思われます。
コンテンツ公開後の効果測定
コンテンツ公開後には、SEOと同様に効果測定を行うことも大切です。
従来の指標(PV数、離脱率など)に加えて、生成AIからの流入数のを計測する必要があります。
GoogleAnalyticsを使用している場合は、セッションの参照元に「chatgpt.com」「gemini.google.com」「perplexity.ai 」など、生成AIからの参照元が計測できる場合もあります。
そのほかには、自身でAIを使用してみて自社の内容が参照されているかどうかを試してみたり、検索結果に表示されるAIでの要約に自社のコンテンツが含まれているかどうかを確認するなどといったことでも効果測定は可能です。
なお、SearchConsoleの標準機能ではAIからの要約でのクリックを直接確認することはできません。
ただし、要約された内容からのクリックがある場合は、総クリック数には含まれているので、他のデータを組み合わせて間接的な分析を試みることは可能です。
AIの影響力が増加している時代なので、今後GoogleAnalyticsやSearchConsoleなどのツールでもより詳細にAIからの流入の効果測定を行う機能が追加される可能性があるので、注意してみておきましょう。
まとめ
現時点では影響力が大きいということではないGEO/LLMOですが、今後の世の中の動きによっては最重要施策になる可能性もあります。
技術的な側面で現時点で必須の対策はないのですが、今後は構造化データや必須タグなどが発表される可能性もあるので、AI関連のニュースは多いですが定期的にチェックしておくことを心がけておくとよいのかなと思っています。