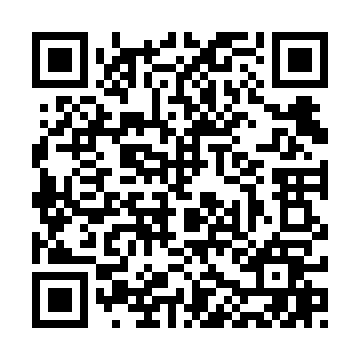第45回リクリセミナー「帰ってきたWebデザイントレンド & A11y Osaka Meetup」参加レポート
Publish2025/07/16(水)

2025年7月12日に大阪産業創造館で行われた第45回リクリセミナー「帰ってきたWebデザイントレンド & A11y Osaka Meetup」に参加してきました。
当日の振り返りを兼ねて、どのような内容だったのかの紹介記事を書こうと思います。
余談ですが、この記事を書くにあたって当日のスライドを見返したり、当日のXのポストを追ったりした結果、内容を復習することになっているので、セミナーとかに行った人は自分で考えて記事を書くといいと思います。
当日のXのポストは「#resem45」でまとめられているので、チェックしましょう。
では本編。
帰ってきたWebデザイントレンド
今回のセミナーは、「帰ってきたWebデザイントレンド」からスタート。
Webデザイントレンドは以前から何回か見たことがあるセッションで、ここ最近のwebサイトのデザインの傾向や方向性をデザイナーの視点で観察するというものなのですが、特徴として一番大きいなと思っているのが、確認しているサイトの数がすごいというところにあると思います。
実際に今回の場合は、海外2,000/スタートアップ218/AI関連350/グローバル400/上場企業3,000/自治体1,700のサイトを巡回して確認しているということで、その圧倒的な量に驚かされます。
しかも、さらにすごいのはそのサイトも一時的に確認しているのではなく、年数を跨いでスクリーンショットを保存しているという徹底ぶりなので、普通に「そのサイトの数年前のものがこちらで」のようにサラッと紹介されていましたが、ここは普通にすごいところだと思っています。
最近は自分自身がデザインをすることはほぼなくなりましたし、デザイン自体への関心も以前に比べると下がっている自覚はあるのですが、世の中の動向や潮流くらいは知っておきたいとは思っているので、今回の内容はすごく参考になりました。
海外サイト編
まず海外サイト編では、ジオメトリック/ホバーサムネイル/終始横スクロールというトピックがありました。
ジオメトリックを使ったサイトが海外では多いと思っていたので、この辺は自分の感覚と同じだなーと思って聞いてました。
個人的な印象ではあるんですけど、逆に日本ではジオメトリックの要素は部分的に取り入れられることはありますが、サイト全体の印象的にメインで使うことっていうのがほぼないので、こういうところが国民性といいうかその地域ごとの特色として出やすいんやろうなと思いました。
もちろん日本語と英語の文字の影響というのも大いにあると思うんですけど。
ホバーサムネイルについては、個人的にはこれはないなと思ってしまった要素ではあります。
一見するとクリックせんでもその先がわかるのは優しいような気もしないでもないですが、ホバーさせることでそれを実現する時点でスマホがメインの閲覧環境になっている今の時代にあえて使うようなものでもないんじゃないかなと思います。
終始横スクロールについては、普通に使いづらいというか、これまでのユーザー体験の蓄積で縦にスクロールするのが一般的である以上横にスクロールすることで斬新さは演出できても、結局使いづらいという印象になると思うので、かえってユーザー体験を損ねる結果になるのでは?と思っています。
なんか否定的な意見ばかりになってしまってますが、新しい方向性を探っているアプローチの方法としては面白い取り組みかなとは思います。
スタートアップ編
スタートアップ編で気になったのは、タブの変な使い方とフッターでか文字です。
タブの使い方については、説明されていたように変わった使い方をしているなーと思って聞いてたんですけど、お作法的には正しくなかったとしても、その結果がユーザーにとって使いやすく理解しやすいものであればいいのでは?と思っている方なので、取り組みのスタンスとしては結構面白いのではないかなと思います。
フッターでか文字は、どうしてもウェブライダーのことを思い出してしまいます(笑)
なので、今に始まった事ではないしなーと思う感情もあり、その辺が結構微妙ではあるんですけど、伝えたい感情としては理解はできました。
AI関連編
AI関連編では、やはり影響力が大きすぎるChatGPTの影響で、いきなりアプリのような画面で始まるサイトが増えたというのが印象的でした。
一番メジャーどころのスタイルを模倣することはある意味ユーザービリティ的にはよいような気もするので納得ではあります。
(違うプロダクトやサービスのUIなどを模倣することが良いということではないので注意が必要)
ただ、そのまま真似しているわけではなくて、似たような感じにしてはいるものの、すぐに使えるサイトは少なくてサインアップが必要な場合が多いというのも、まあそうやろうなというのが正直な感想でした。
矢野さんもおっしゃってましたが、サービス提供側視点で考えるとアカウントの獲得が最優先事項なので、すぐに使えるよりはサインアップして使ってもらう方がいいのは当然ですよね。
当然ではあるのですが、ユーザー視点からするとうーんとなるポイントではあるんですよね。
とっかかりは使えるけど、これ以上使う場合はアカウント作ってねとか、その辺のさじ加減がうまくできているサービスが増えてくるといいのかなとか考えてました。
途中で紹介されていたサービス模式図は、個人的にはめっちゃわかるなと思って聞いてたんですけど、以前サービス系のサイトを作っているときに、どうしてもサービス内容が複雑で専門的な場合、文字ではなく図形やイラストなどでまとめた方が分かりやすいということっていうのは結構あるんですよね。
そういう点で考えると、AI関連のサービスもどういうものでどういったことができるのかを理解するのが難しい内容だと思うので、模式図を使うことで理解度を上げていこうというアプローチは非常に理にかなっていると思います。
あと、AIという特性上どうしてもイメージに冷たい印象があるためか、その部分を解消するためにサイトの配色でベージュを使うなどして優しさや温かみを出す演出をしているっぽいというのも面白い視点でした。
グローバル編
グローバル編では、アクセシビリティオーバーレイとカルーセル、ゆったり感というのがキーワードになってました。
アクセシビリティーオーバーレイはサイトの導入するアクセシビリティ対応のためのツールチップのようなもので、グローバルサイトなので多くのユーザーに快適に見てもらえるための対応策の一つとして導入されているんだろうなと思いました。
カルーセルについては、グルーバルサイトではカルーセルの導入が盛んで、中にはフルカルーセルのページがあるサイトまで出てきて、どんだけ好きやねんと思わずツッコミを入れたくなるほどでした。
色々な問題点は一旦置いといて、フルカルーセルとかはある種の一つのゴールなのかもしれないと思うほど、取り憑かれている印象でした。
あと、グローバルのサイトでは余白を生かしたデザインが増えてきているということで、情報過多の時代だからこその揺り戻しとかもあるのやもしれないのかなとか考えてました。
原さんの目
原さんの目のコーナーでは、緊急情報の扱いに触れていましたが、緊急情報はボタンでまとめるような方向性が増えてきたとのことです。
一時期に比べれば緊急情報が多く出るような時代ではなくなったとはいえ、緊急情報を出さないといけない時のために事前に準備しておくような運用を行なっている企業や団体が増えてきているんだなと思います。
これがいいことなのか悪いことなのかは判断が難しいことではありますが、サイトでどういう情報を出していく必要があるのかを考えた結果として一旦こういう形になっているのであれば、それが自然の流れなのかなとも思います。
上場企業編
上場企業編では、オリジナルな要素を持つグローバルメニューなどが出てきているということがポイントとして挙げられていました。
JRの運行状況など、サービスに連動して顧客満足を高めるものが目につくとのことです。
また、角丸の変則的な変化を使うパターンも増えているようで、見せ方のアプローチとしてなんとなくですが煮詰まってきている感があるなと感じて聞いていました。
ただ、上場企業編ではとても面白い発見があったんです。
それが「早わかり」。
企業の特徴やポイントなどをわかりやすく3分とかで理解してもらおうという取り組みで、情報の処理速度を求められている現代っぽい取り組みだと思って聞いてました。
某匿名掲示板とかで「3行で」と言われているようなアプローチを企業でも取り入れていこう、短い時間で知ってもらおうというアプローチはいろいろなシーンで展開できそうで結構いいなと思っています。
これはけっこう今すぐにでも導入しやすいアプローチなので、何か展開できそうなものがあれば取り入れてみようかなとも思いました。
矢野さんの目
矢野さんの目のコーナーでは、動画についての言及がありました。
動画を使用することで、エンゲージメントやシェア率も上がるというのは、普段Analyticsで見ている結果からも納得のものだったので全く異論がないなと思って聞いてました。
自治体編
自治体編では、ここでも自治体ならではのコンテンツが出てきていることに驚かされました。
まずは「ここだよマップ」。フッターや所在地などの部分に、地図上だとここにあるということがわかる画像などを配置して、日本のどの箇所にある自治体なのかを表示するという試みです。
自治体のサイトなので、基本的にはその自治体を知っている人向け(住んでいる人や移住を検討する人など)の内容だと思うんですけど、位置がどこなのかを知らない層にも見られていることを認識して意識していることがわかり、非常に面白いなと思いました。
そして、知らなかったのが「ページID」
ページIDという名称からするとWordPressの記事や固定ページに割り振られている固有の数値/パラメーターのようなものをイメージしてたんですが、自治体サイトでのページIDというのは自治体が発行している刊行物に記載されているIDのことのようです。
発行している印刷物のページ内にある情報をページIDとして設定し、webでその内容を確認する場合はそのページIDで検索するという、ある意味クロスメディ対応と言える取り組みでした。
普段自治体のサイトや自治体からの刊行物とかを意識してなかったのですが、改めて僕の住んでいる高槻市で調べてみるとページIDが導入されていました。
高槻だけなんかなと思って調べてみましたが、全部の市町村ではないものの、結構な導入事例があったので全国的な共通ルールということなんでしょうね。
これは普通に参考になりました。
そして、自治体サイトのビジュアル表現として、名産/特産モチーフに振り切るパターンが特徴的というのも面白いポイントでした。
原さんもおっしゃてましたが、地域の特産品って一つや二つじゃないんですよね。
こっちを取り上げればあっちから不満が来るというように、複数の特産品や名物がある場合、揉めるケースもあると思うんですけど、それも分かった上で一つのモチーフに振り切る自治体があるというのが非常に面白いと思いました。
坂本さんの目
坂本さんの目のコーナーでは、坂本さん自体が最近抱えている問題を踏まえた上で、こういうサイトだと助かるという事例が非常に参考になりました。
まず、24px(csspx)の領域確保については、PCでもそうですしスマホの場合でも誤クリック/誤タップを防ぐ意味でも強く意識しておくことが大事だなと改めて思いました。
そして、メガメニューの動作では、キーボード操作でメガメニューを閉じたい、キーボードのESCで制御できるとこれだけ助かるというメッセージが強く残りました。
(この熱意が次の前振りになっているとはこの時点で気付きませんでしたが)
おまけ
以下については、セッション中に話されていたことではなくて、当日資料の中にあったおまけについてなんですが、2つ面白いなと思ったことがあったので書いておきます。
1つ目は縦書きについて。
サイトで縦書きを使う場合って、これまでだと画像化したものを使用するというのが一般的な対応だったと思うのですが(自分の認識が古いというのはもちろんあるけど)、今回紹介されていたサイトではCSSの「writing-mode」で対応されていました。
そういえばそういう形での対応もできるねと思い返し、今のブラウザ側の対応状況ってどうだろうなと思ってcaniuse.comで調べてみたところ、ほぼ問題なくどのブラウザでも対応しているという状況がわかりました。
https://caniuse.com/?search=writing-mode
今すぐ使うかと言われればそうでもないのですが、今後縦書きの方が有効な場面が来たら使ってもいいかもしれんなと思っています。
2つ目がアイコンを工夫しているサイトが増えたという点です。
アイコンといえば、マテリアルデザインに入っているものを使用するというケースが多かったと思っていたのですが、オリジナルの要素をアイコン化したり、これまでにもあったアイコンをさらにわかりやすいように変更したりといった取り組みがいろいろなところで行われていたというのが非常に面白いと思いました。
アイコンのように、パッと見ただけでそれが何を意味するのかを識別するための仕組みというのは、一般的な認知の拡大が大きい方が効果的になるので、ある種マテリアルデザインのアイコンがいろいろなサイトで使われることによってユーザーの理解度が上がるということにもつながっていた側面もあると思っているのですが、アイコンをさらにわかりやすく工夫することで、一歩先の使いやすさと認知の向上を目指している姿勢というのが非常にいいなと思ったわけです。
だいぶ長くなりましたが、デザイントレンドのセッションを聞いて感じていたことはこういうことでした。
スポンサーセッション a-blog cms
デザイントレンドの次は、スポンサーセッションとしてa-blog cmsのセッションがありました。
a-blog cmsは、こちらでもとある案件で使っているシステムなので、どういうものかは理解しているのですが、個人的に面白いなと思ったのはCMSの現状の利用状況のデータでした。
この2つがそのデータですが、WordPressがやっぱり異常なほど多いというだけでなく、いろいろなツールでひしめき合っている状況というのが非常に面白いですね。
https://w3techs.com/technologies/segmentation/cl-ja-/content_management
https://oshiete-url.jp/report/cms/2024_8/
スポンサーセッション CPI
2つ目のスポンサーセッションは、CPIさんのセッションで、今開発を行なっているスマートリリースUについての内容でした。
スマートリリース自体は以前から知っているものの、今の案件では使うのはちょっと問題がある(システム的に悪いということではなくて、今の運用形態とマッチしていないという理由)ので使ってはいないのですが、新しく作られるスマートリリースUだとこういうことができそうというイメージがわかる内容でした。
個人的に色々と思うところはあるのですが(具体的な話は交流会の時にCPIの中の人と話してすっきりはしているので割愛)、応援したくなるプロジェクトですし、こちらでも実用できるシーンがあれば利用したいなと思える内容でした。
ウェブアクセシビリティmeetup
最後のセッションは「ウェブアクセシビリティmeetup」です。
デザインの話を聞くのも久々でしたが、アクセシビリティの話を聞くのも久々で、こちらも今回すごく楽しみにしていました。
結果から言うと、聞いていく過程で自分の至らなさや惰性でしていた部分、反省しないといけない部分などがはっきりわかってきたので、ものすごく聞いてよかったなと思えるセッションでした。
また、今回はコードの話ではなく見た目の話でのアクセシビリティについてということもあって、これまでアクセシビリティのことをあまり考えていなかったり難しいと思って避けていたデザイナーさんとかでも考えるきっかけを与えるいい機会になるアプローチだったと思える内容だったので、そういう点でも非常によかったと思っています。
LDについて
まず最初に、今回登壇されているTenさんが自身の持っているLD(Learning Disabilities : 学習障害)について紹介してくれました。
僕自身はLDのことを名前は知っていたものの、どういった種類のものなのかを正しく把握できていなかったので、非常に勉強になりました。
LDでは読字障害/書字障害/算数障害という3つのパターンがあり、それぞれで抱える問題が違っているという点は認識しておく必要があると思いました。
LDの特徴を持つ人をディスレクシアという名称で呼んでいることがあるのですが、ディスレクシアの人の場合、今回のデザイントレンドで紹介したサイトでどういう問題が発生するのかという実例が非常に興味深かったです。
ホバーサムネイルとアイコン位置
ホバーサムネイルのところでは、画面を拡大して閲覧しているとホバーサムネイルの影響で要素が画面に収まらないので非常に使いづらいことになってしまうという問題点の指摘がありました。
これは実例で見せてもらって、「確かにすごくみづらいし使いづらい…」と思ったので、やっぱりこういうアプローチ(ホバーサムネイル)は悪手だよなと思います。
また、画面の拡大にも複数の手段があり、それぞれの方法で拡大の仕様が異なるのでそれぞれのパターン(windowsの拡大鏡ツール/ブラウザ自体の拡大機能など)も想定しておくほうが好ましいという点は結構大きなポイントだと思います。
方法は一つじゃないし、方法によって結果が変わってくるという認識を持つことが大切だなと改めて思いました。
UIの話をしているときに、アコーディオンの開閉ボタンは左にするという説明があって、「なるほど」と思って聞いていたのですが、説明を聞けば聞くほどこういう細かい部分への配慮が不足していたなと痛感しました。
ついつい、これまでの対応の延長で対応しているなと思うところがあったり、これってどうなんだろう?と考えることを忘れてしまっている自分に気付いたんですよね…。
で、それに気付いてからは前で話している内容を聞いて心が苦しくなってきました。もっと反省しないといけないなと心から思いました。
緊急対応とフォーカス
緊急対応のセクションで話していた内容の補足があったんですけど、緊急情報タブは実装する場合に、スクリーンリーダー対応はできているかを検証する、タブ展開時のフォーカス移動順序は問題ないかを確認する(フォーカス位置が正しくなく動作するケースが散見される)ということをふまえて実装する必要があるというのが確かにその通りやでと思って聞いてました。
緊急情報のタブを開いたのに、HTMLの構造上離れた位置にあってフォーカスの位置がおかしくなるケースというのは普通に考えられるケースですが、実装するときにスクリーンリーダーのことを考えずに作っていたら確かにそうなる可能性は高いと思いましたし、スクリーンリーダーのことを考えてコーディングするということを日常的にしていないと普通に忘れてしまうという内容でもありますよね。
こういうところが注意しないといけない点だなと思うわけです。
また、実装面のことだけでなく、そもそもの話で大事なのは自分で要素をコントロールできることだという視点を持つことが大切ですね。
タブのフォーカスもそうですけど、タブ自体のコントロールをユーザー自身ができるようになっているかどうかということも考えて実装しないといけないと思うわけです。
セッション中では、開いた要素をキーボードのESCで閉じる一連の流れを「SAKAMOTO」と呼びましょうということになってましたが(デザイントレンドの坂本さんの熱量がフリになっていて、ここで花開くとは思っていなかったけど、話の流れ的にきれいにまとまったしめちゃおもしろいからこれはこれでアリやなと思って聞いてました)、こういうことなんですよね。
画面の長さと画面占有率
画面の長さについての言及もあり、最近のページはとにかく長い、スクロールの長すぎは注意が必要ということは確かにその通りと思って聞いていました。
今の時代はスマホでの閲覧がメインなので、コンテンツが長いとスクロールも長くなるのですが、どこかで「まあそういうものやし、許容範囲かな」と思い込んでいるところがありましたが、ページが長すぎることによって使うのが大変な人にとってはめんどくさいことこの上無い状態になるというのは確かにその通りでした。
そして、長い場合はページ内リンクを用意しておくと優しいということもまさにその通りで、ユーザーが自分の興味のある内容にすぐ到達できるというのはアクセシビリティという言葉通りでそれが正解だなと思う次第です。
また、サービス模式図の要素は確かにわかりやすい側面はあるものの、その要素自体が大きすぎて画面内に収まりきらない場合は、逆にわかりづらくなるというのもなるほどと思って聞いてました。
その後、スマホの時の固定ヘッダーの話になり、ヘッダーなどのナビゲーションが固定の場合、画面占有率を気にして欲しいという指摘がありました。
サイトによっては画面拡大でスマホを見ていて、ナビゲーションで埋め尽くされて何も中身が見えないケースもあるので、これだと非常に見づらいというのは確かにその通りだと思います。
また、クリック範囲はできる限り広く(広いのに越したことはない)というのも非常に同意で、基本は24px以上というのをここでも言っていたので大切なポイントは共通性があるなと思ってもいました。
アクセシビリティを高めるとユーザビリティも高まる
セッションの途中で入っていた言葉なんですけど、「アクセシビリティを高めるとユーザビリティも高まる」という言葉は非常によいなと思いました。
一つの対応を行うことが総合的に相乗効果を生んで良くなるという状況を作ることができれば、良い形のスパイラルになるのでいいなと感じています。
どうしてもアクセシビリティのみに焦点を当てるとインパクトが弱く感じられる場合というのはあると思うので(この辺は人によって感じ方や前提条件が違うので良い悪いの話ではなくてそういう差異はあるものだと思っています)、相乗効果を産むということがわかっているのであれば説得力も変わってくると思います。
カードUIとフォント/表記
カードUIは、ディスレクシアの人にとって難しいケースがあるという説明も非常に納得感のある説明でした。
具体的な例を見ながら、この場合だとこういうふうに見えてしまうのでわかりづらいという説明はとても説得力があると思いました。
ポイントとしては、文字だけだと認識できない場合があるので「文字とアイコンの併記する」「境界線をはっきり区切る(線や枠も使う)」「要素の頭を揃える」というポイントを抑えることでかなり改善しそうかなとも思いました。
この辺については、サイトのデザインのトンマナとかも影響しているので、対応が難しいと思われる場合もあるかと思いますが、可能な範囲で誤認をしないようなデザインにしていく努力は必要だなと感じています。
また、この話の面白かった点として、サイト上に表示されているテキストを自分の好きなフォントに変えて見ている人がいるというのも「なるほど、そういうケースもあるのか」というポイントでした。
ディスレクシアの特徴を持っている人の場合、フォントによって文字の認識度合いが違ってくるので、可能な限り見やすいフォントを使用してサイトを閲覧したいというニーズがあるというのは押さえておきたいポイントです。
また、漢字をひらくことで可読性が上がることもあるし、金額表記は記号ではなく漢字にすることで認識されやすくなるというところなどは、細かい部分ではあるのですがこういう部分もしっかり把握して対応していくことでサイトにとっては使い勝手が良くなる要素なので、気をつけていきないところやなと思いました。
アクセシビリティオーバーレイ
デザイントレンドで取り上げられていたアクセシビリティオーバーレイについては、実際にどういうことができるのかをデモしながら説明してくれたのが非常にわかりやすかったです。
機能として紹介されていた「ルーラー」とか「スクリーンマスク」などは、使ってみると確かによさそうなところもあるので、おもしろいツールではあるのかなと思いました。
ただ、その後の説明にもありましたがこういうツールは根本的な解決をするアプローチではなく、あくまで補助的なものなので、このツールを導入すれば解決するということでは無いので使用には注意が必要です。
アクセシビリティの悪いサイトでは訴訟が起こる欧米では、実際にアクセシビリティオーバーレイを使ったことで訴訟されるケースなどもあり(使わなければ訴訟されなかったと考えられるケースがある)、使うこと自体が問題の原因になることもあるというのも結構な驚きです。
そういうことであれば、そういうツールがあるということを知っておくだけで実際には使わず、するのであれば根本的な解決方法でアプローチしていくのが正解かなと考えています。
セッション中に何度か出てきた言葉、「気をつけよう、甘い言葉とオーバーレイ」。こういうことだと思います。
カルーセル
カルーセルについての言及もあり、カルーセルはやはりアクセシビリティ面で考えると問題の原因を作る可能性がある、非常に取り扱いが難しいものだなと再認識しました。
何よりも問題なのは、カルーセルのように自分の意思とは無関係に動作する要素を自分で制御できない場合に、大きな負担になってしまうということが問題です。
カルーセルを使う場合は停止ボタンは必須で、実装するのであれば自身で動作をコントロールすることができるようにしておくことが最低限のマナーだと思いました。
手話
手話についても言及があったのですが、その内容も非常に興味深いものでした。
僕もこれまで手話についての意識が足りていなかったと反省しきりなのですが、普段のコミュニケーション手段が手話の人の場合、文字でのやり取りは分かるけどストレスを感じるケースもあり、できれば手話で済ませたいというニーズはあるということは完全に抜けていた視点でした。
使うことはできるし、どういうことかも理解はしているけど、使いづらいからできれば使いたく無いものっていうのはあるので、それが文字でのコミュニケーションの場合もあるというのは忘れがちですが忘れてはいけないことだと思うんですよね。
手話がその一つになっているという点は、普段手話を使わないからわからなかったんですが、そういう点も含めて意識が低いと言わざるを得ないですね。反省します。
また、手話には方言があるというのも知らないことでした。
この辺は手話にこれまで興味を持っていなかったことが全ての原因なような気がしています。意識が低いということですね。
そしてこの話を聞いて個人的にかなり問題を感じたので、セミナーが終わった次の日にデザイントレンドで紹介されていた手話ツールについて改めて考えてみました。
できれば手話を使って認識をしたいと考える人にとって、手話ツールの導入はかなり大きなうれしいポイントになる可能性があります。
なので導入することはかなりよさそうと思う反面、僕のように手話のことをよくわかっていない人が導入した場合、導入することが目的になって導入したツールが喜ばれる品質のものであるかどうかの判断ができないというのが問題だと思います。
英語サイトなどでも起こることですが、多言語のサイトを作る場合、ネイティブな方からするとおかしな言葉や表現になっていることがあり、かえって使いづらいものになってしまうということがあります。
手話でも同じように、手話にも方言があるくらいの多様性があるわけなので、仮にツールを導入したとしても導入したツールのクオリティ検証ができないのは問題です。
この問題を解決するには、手話のできる方に検証をお願いするということになるのですが、そういう方をどうやって探してどういう形で協力してもらえるのかを交渉する必要もあるので、なかなかハードルが高くなります。
もしくは、自分自身が手話への理解度を高める(手話でコミュニケーションができるようになる)という解決方法もありますが、これも結構ハードルが高い…。
ツールの導入をしないよりした方がいいけど、検証が難しいし導入自体が効果的では無い可能性も出てくることを考えると、かなり考え所ではありむずかしいなと色々考えてしまいました。
まとめと感想
今回、リアルでのセミナーにかなり久々に参加しました。
リアルでの参加は登壇者の方の話に集中できるので、その時間内での集中力などを考えると非常にいい時間になるのがいいですね。
オンラインだとどうしても意識が散漫になるタイミングがあるので。
そういう点で久々に色々なことに向き合える時間ができたということもよかったですし、何より話の内容がとてもよかったです。
デザインとアクセシビリティに共通することとして、「相手に情報を伝える」ためにどうするのがいいのかということを考え、実践していくところは共通だと思っているので、その共通点から今回の場合はどうだろうと考える機会があって、そのことを考える時間を作って過ごせたことは自分にとってもいい時間の使い方だったなと改めて思います。
こういう場所をセッティングしていただいた運営の皆さんには感謝しています。
また、登壇されていた皆さんもこの内容の準備は想像以上に大変だったと思います。
本当にありがとうございました。
また次回も来年あることを期待して、開催されたらぜひ参加したいと思います。